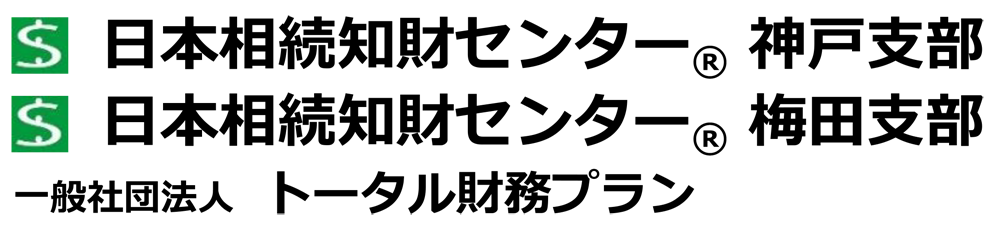ご自身の思いを形にし
円満な相続のために
遺言は、人生の最後に大切な想いを託す手段です。
遺言によって「どの財産を、誰に、どのように継承させたいか」を明確にしておくことで、残されたご家族が相続をめぐる争いに巻き込まれることを防ぐことができます。
記載できる内容は主に相続や財産の分配に関する事柄に限られていますが、「付事事項」を添えることで、判断に至った理由やご家族への感謝の気持ちなども伝えることができます。

一方で遺言がない場合、相続人は遺産分割協議を通じて分配を決めることになります。
しかし突然手にする遺産を巡る話し合いは円滑に進むとは限らず、しばしば家族間トラブルへ発展する例もあります。
さらに、遺言が法律的に不備を含んでいると、意図せず無効になってしまうリスクもあります。
そのため、「公正証書」で遺言を作成しておくことで、法的に不備がない有効な遺言にすることができます。
遺言を遺すことでできること
01|特定の相続人に多くの財産を遺せる
遺言書がなければ遺産分割協議で分配を決めることになります。話し合いが円滑に進まず、関係が悪化することも少なくありません。遺言を用意しておけば「老後の世話をしてくれた子に多く渡したい」「事業を継ぐ子に株を相続させたい」といった希望を反映できます。
02|相続人でない人に財産を遺贈できる
遺言がない場合、相続人がいなければ財産は国庫へ帰属します。相続人以外へ渡したい人がいても、遺言がなければ叶いません。近年は社会貢献団体や学校・研究機関などへの寄付も増加しています。
03|遺言書を作成しておけば、相続人が認知症になっていたとしても相続手続きができる
認知症の相続人は遺産分割協議に参加できず、成年後見制度を利用する必要が出てきます。後見人が選任されると、その人が亡くなるまで後見は続きます。遺言書を作成しておけば、遺言執行人が遺言通りに財産を分けることができます。
04|海外に住む相続人に負担をかけずに相続手続きができる
海外居住の相続人は、日本の住民票や印鑑証明書に代わる証明を現地で取得するなど煩雑な手続きが必要です。遺言書で「遺言執行者」を指定しておけば、円滑に遺言内容を実行することが可能ですので、海外に子どもがいる方には特に有効です。
05|未成年の相続人がいても、特別代理人を選任せずに相続手続きができる
未成年は法的行為が制限されており、自ら相続手続きを行えません。さらに親が相続人の場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てが必要となります。遺言があれば特別代理人を立てずに、遺言執行者が遺言内容を実行することができます。
遺言書を作成しておいた方がいいケース
\1つでも当てはまる方は無料相談にてご相談ください。/
| 不動産を持っている人 | 相続人が複数いれば、不動産の分配を巡り争いが起こりやすくなります。特に自宅以外の遺産がない場合や、共有不動産・所有者が異なる土地建物がある場合は注意が必要です。 |
|---|---|
| 子どもがいない夫婦 | 配偶者が亡くなると、その親や兄弟姉妹が相続人となり協議が必要となります。自宅や夫婦で築いた財産にも他の相続人に権利が及ぶため、全財産を配偶者に残したいなら遺言が不可欠です。 |
| 未成年の子どもがいる人 | 自分以外に親権者がいない場合、遺言で信頼できる人を未成年後見人に指定しておくことで、未成年後見人に子どもの養育、財産管理、契約などを任せることができます。遺言で指定していない場合は、親族等の申立によって家庭裁判所が未成年後見人を選任することとなります。 |
| 独身の人 | 相続人や特別縁故者がいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。お世話になった人や公共団体へ寄付したい場合は遺言が必要です。 |
| 兄弟姉妹の仲が悪い人 | 遺産分割協議がまとまらず関係が断絶する恐れがあります。争いを避けるために遺言を残しておきましょう。 |
| 相続人が海外に 住んでいる人 | 遺言がないと在外公館で証明を取得する必要があり、手続きが煩雑になります。 |
| 遺産の内容を 相続人が把握していない | 死後に借金が見つかるなど混乱が生じることも。遺言と併せて財産目録を作成しておくと安心です。 |
| 相続人以外で 財産をあげたい人がいる | 内縁の配偶者や義理の子、世話をしてくれた親族などに財産を残したいなら遺言が必要です。 |
| 前妻(夫)との間に 子どもがいる人 | 前妻(夫)との子にも相続権があり、その子と遺産分割協議を行わないと相続手続きができず、場合によっては争いが起こる可能性もあります。第三者の専門家を遺言執行人に指定することで直接の交渉を避けることができます。 |
遺言公正証書作成の手続きの流れ
ご希望に沿う遺言が作成できるよう、十分なヒアリングを行います。
ご依頼後、戸籍謄本など必要書類をお預かりします。
また、財産目録を作成し、財産の洗い出しを行います。
相続税や納税を考慮した遺産分割・遺留分を考慮した遺産分割を、税務、法務の面からアドバイスいたします。
遺言書の案文を作成
遺言書の内容が希望に沿っているかを確認、修正をおこないます。
相続人などとのご関係を考慮し、最善の文案を提案します。

ご依頼事項に合わせてお見積りいたします。
詳しくはご相談ください。